統合失調症の治療や回復の過程で、家族との関係は非常に大きな影響を与えます。支えになる一方で、感情のすれ違いや過度な干渉がストレスとなり、再発リスクを高める要因にもなります。
今回の記事では、心理学的な概念「EE(Expressed Emotion=感情表出)」をもとに、家族とどのように距離を取り、健全な関係を保っていくかを解説します。
EE(感情表出)とは? ― 家族関係に影響を与える3つの要素
EEとは「感情の伝わり方」のこと
EE(Expressed Emotion)とは、家族や周囲が本人に向ける感情表現の度合いを示す心理学的な指標です。これは「愛情の有無」ではなく、どれだけ感情的に関わっているかを測るものです。EEが高い家庭では、本人がプレッシャーを感じやすく、再発率が高いことが多くの研究で確認されています。
EEというのは、主に患者さんに対し攻撃的であったり、批判的になったりすると上がりやすいですが、それ以外にも、過保護になりすぎても上がりやすいというデータがあります。ですから、適度な関係性が重要になるのでしょう。
EEの3つの特徴 ― 批判・敵意・情緒的巻き込み
EEを構成する主な要素は以下の3つです。
- 批判(Criticism):本人の言動を否定的に評価する
- 敵意(Hostility):怒りや苛立ちを表す
- 情緒的巻き込み(Emotional Over-Involvement):過度に世話を焼く、干渉する
これらは「愛情の裏返し」であることも多く、家族に悪気がなくても本人には強いストレスになります。愛情というのは、意外と難しい感情であると感じます。なぜなら、支援者が良かれと思ってやったことも、実は患者さんにとってはストレスになってしまう、みたいな事態になりやすいからです。ですから、バランスが大切になってくるのです。
なぜEEが高いと再発リスクが上がるのか?
過度な干渉がストレスを生む
統合失調症の症状は、ストレスによって悪化する傾向があります。家族の「心配だから」「助けたい」という気持ちが、結果的にプレッシャーになってしまうのです。
たとえば、
- 「ちゃんと薬飲んでるの?」
- 「いつになったら働けるの?」
といった言葉が、本人には「責められている」と感じられることがあります。私の家族は幸いなことに理解があったのですが、知り合いの統合失調症の患者さんの話では、「いつまで寝ているの?」という言葉が一番痛かったと言っていました。動きたくても動けないというジレンマをもっとわかってもらいたいと思います。
安心できる距離が回復を支える
家族がすべてを抱え込まず、適度な距離感を保つことが、結果的に本人の自立を助けます。物理的な距離だけでなく、心理的な余白を持つことが大切です。お互いが「依存でも放置でもない関係」を築くことで、安心して暮らせる土台が整っていきます。
ただ、適度な距離感を持つというのは意外と難しかったりします。ただわかってもらいたいのは、患者さんを突き放すのではなく、そばにいるというか、そこで話を聞くという姿勢だということです。そばにいるという姿勢は、非常に大切だと感じます。
家族と距離を保つための具体的な工夫
感情的になったら一歩引く
感情が高ぶった時こそ、「今は話さない」勇気を持つことが大切です。お互いに冷静さを取り戻してから会話することで、不要な衝突を防げます。私自身も、イライラした時は別の部屋で休むようにしています。その「間」があることで、関係を壊さずに済むことが多くなりました。
誰にでも一人になりたい瞬間はあると思います。そして、統合失調症の患者さんにも一人で考える時間は大切です。ただ、家族や関係者の人にわかってもらいたいのは、患者さんに一人で考える時間を与える一方で、そばにはいてくださいということです。
「感謝」と「線引き」を両立させる
家族に支えてもらっていることへの感謝を言葉で伝えることはとても大事です。ただし、頼りすぎず、できることは自分でやる姿勢も同じくらい重要です。
たとえば、
- 服薬や通院の管理は自分で
- 家事を一つでも分担する
といった小さな行動が、家族関係のバランスを保つ助けになります。意外となんでもやってあげるというのはよくありません。患者さんの自尊心を傷つける要因となってしまうのです。ですから、簡単でいいので、何か仕事を与え、家族の一員として認めてあげましょう。
家族側の理解と協力 ― 支え方を“変える”という選択
支援は「指導」ではなく「共感」から
家族ができる最も大切なサポートは、正解を教えることではなく、気持ちを受け止めることです。「どうしてできないの?」ではなく、「今日は大変だったね」と寄り添う言葉が、本人の安心につながります。
支援の形を指導から共感に変えることで、EEの高さを自然と下げることができます。EEが高い状態が続くと、再発のリスクが上がります。そして一度再発すると治りにくくなるという特徴があるので、適度な関係性を作り、EEを下げる必要があるのです。
専門家や支援機関と連携する
家族だけで抱え込まないことも重要です。地域の精神保健福祉センターや家族会、医療機関のソーシャルワーカーなどに相談することで、客観的なアドバイスを得られます。専門家と一緒に「関わりすぎない支援」を設計することで、家族の負担も軽減され、本人も安心して回復に集中できます。
家族だけではどうしようもない時もあるでしょう。だからこそ、地域の福祉サービスが重要になるのです。特に家族会などに参加して、他の家族の様子を知っておくと、自分たちの関係性の修復にも活かせることが多いので、非常にオススメです。
【まとめ】家族との距離は「冷たさ」ではなく「信頼の形」
EE(感情表出)は、決して悪いものではありません。大切なのは、「感情の量」ではなく「伝え方」です。最後にまとめとして、下記のポイントを忘れずに守るようにしてください。
- 批判や干渉ではなく、共感と見守りを意識する
- 感情的になったら距離をとる
- 感謝と自立をバランスよく持つ
家族が「本人の生活を全部支える」のではなく、「回復の環境を支える」こと。その意識の変化が、再発を防ぎ、より穏やかな日常へとつながっていきます。患者さんを支えられるのは、家族であるのは間違いありません。ですから、この記事を参考にして、支援の方法を考えるようにしてください。
▶ 動画はこちらからご覧いただけます
💬 統合失調症の回復に影響を与える“家族との距離感とEE(感情表出)”について解説。
家族関係で悩んでいる方や、支援する立場の方にも役立つ内容です。
統合失調症の患者さんとの適度な関係の作り方をまとめた記事はこちらです⬇️

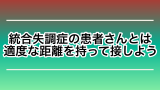


コメント