こんにちは、ウッチーです。
「統合失調症になる自我障害が出るって聞くけどどうなの?」
と、こんな疑問を覚える当事者も多いようです。
結論からお話しすると――。
「統合失調症になると、自我の壁があいまいになり、周囲からの影響を受けやすくなります」
と、いうことが言えます。
今回は、統合失調症の自我障害を理解するポイントや対策をまとめました。
この記事が、統合失調症の自我障害について調べている方の参考になれば幸いです。
本記事はこんな方にオススメ
- 統合失調症の自我障害を調べている方
- 自我障害を感じており対策などを調べている方
□まずは理解しよう!「自我障害」とは?
統合失調症になると、自我障害が出やすくなります。
とはいっても、「自我障害」って結構難しい言葉ですよね?
まずは、自我障害についてみていきましょう。
自我障害とは?
自我とは、自分と他人をわける意識のことです。
つまり、「これが私だ」という認識を指します。
そして、自我障害とは、その自我の壁がもろくなり、周囲から影響を受けやすくなる状態です。
そうなると、自分の考えと人の考えの区別があいまいになり、起こるケースが多くなっています。
統合失調症には「幻覚」「妄想」とは違い、自我障害は気づきにくい面があるのです。
自我障害には、こんな症状があります。
- 自我漏洩体験
- 考想伝播
- 思考吹入
などがあります。
自我障害の症状① 自我漏洩体験
これは、自分の秘密が周囲に知られていると錯覚してしまう症状です。
自我障害の症状② 考想伝播
これは、自分の考えが周囲に伝わっていると思い込んでしまう症状です。
自我障害の症状③ 思考吹入
これは、相手の考えがわかるとか、伝わってくると感じる症状です。
また、自分の意思ではなく、他人の意思によって操られるという作為体験も統合失調症の症状の一つになっています。
□しっかり抑えよう「自我障害」を理解するポイント
自我障害を理解するポイントがありますので見ていきましょう。
それは――。
- その人らしさを大切にしよう
- 病気よりも本人の困りごとに目を向けよう
- 本人の意思を尊重し自分で決めて進められるようにサポートする
- 今できていることに目を向けよう
この4つです。
1つずつ見ていきましょう。
自我障害を理解するポイント① その人らしさを大切に
統合失調症という病気は、その人のほんの一部です。
ですので、病気であろうと、なかろうと患者さんを認めてあげましょう。
例えば――。
- どんなことが好きなのか?
- これだけは譲れないこと
などを理解し。患者さんが自分らしくいられるようにして向き合いましょう。
自我障害を理解するポイント② 本人に目を向ける
自我障害を患うと、どうしても言動がおかしくなります。
ですが、おかしいことを言っているから、放っておくなどは止めましょう。
実は、患者さんの言葉の背景には、その人を知る答えが隠されているのです。
例えば――。
- 食事作り
- 掃除・片付け
- 金銭管理
など、生活面での困りごとを、一緒に考えて解決していくと、効果的です。
自我障害を理解するポイント③ サポートする
統合失調症の患者さんを抱えると、家族や支援者の想いが先行してしまいがちです。
ですが、まずは患者さん本人がどうしたいのかに目を向けましょう。
自我障害を理解するポイント④ 今できることに目を向ける
統合失調症はゆっくりとしか回復しません。
ですので、周囲の方が焦ったり、過度に期待したりすると、患者さんには負担になります。
再発のリスクにつながるので、患者さん本人のペースを尊重してください。
今できることに目を向け、肯定的に受け止めるようにしましょう。
以上のようなポイントがあるので、あわせて参考にしてみてください。
□必ず確認して!「自我障害」が出た時の対策
自我障害が出た時は、しっかりお薬を服薬するのが大切です。
しかしながら、薬物療法と並行してリハビリをすると効果的なので見ていきましょう。
- デイケア
- 作業療法
- SST
- 心理教育
などが、自我障害の対策として有効です。
それぞれ1つずつ見ていきましょう。
自我障害の対策① デイケア
デイケアというのは、精神障害を抱えた方に向けた、日帰りのリハビリサービスです。
次のような効果があります。
- 生活リズムが整う
- コミュニケーション能力が高まる
- 病気に対しての理解が深まる
- 友人ができて安らぎにつながる
- 社会復帰を目指せる
などの効果があり、自我障害の対策としても有効です。
デイケアについてはコチラの記事でも詳しく解説しています↓
自我障害の対策② 作業療法
作業療法も有効なリハビリの1つです。
主に生活能力や社会適応能力を高めます。
また、心身の機能の回復もはかれるのです。
具体的には――。
- 手工芸
- スポーツ
- 園芸
- 音楽
- 芸術活動
などのレクリエーションを通して、楽しくリハビリしていきます。
作業療法についてはコチラの記事でも詳しく解説しています↓
自我障害の対策③ SST
SSTはロールプレイという実演を通して、困難に直面した時の対策を学びます。
精神疾患を抱えても、社会生活を送る必要がありますよね?
社会生活を送るためには、対人関係を良好する必要があります。
対人関係が上手くいくと、生活の質が上がるのです。
また、SSTでは、病気やお薬との向き合い方、ストレスなどの対処法などを学べます。
SSTについてはコチラの記事でも詳しく解説してします↓
自我障害の対策④ 心理教育
心理教育は、近年注目されているリハビリの1つです。
主に――。
- 病気に対する理解
- 薬物療法の意味
- リハビリテーションの知識
など、総合的に学べるようになっています。
病識が深まると、治療にも前向きになれるので、とてもオススメの治療法と言えるでしょう。
心理教育については、コチラの記事でも詳しく解説してします↓
このようなリハビリを通して、自我障害の対策をしていくと、効果があるでしょう。
□「自我障害」を乗り越え治療を進めましょう
自我障害は、統合失調症の症状の中でもわかりにくい面があります。
まずは、患者さんを理解するのが重要になるでしょう。
最後にまとめとして本記事で紹介した内容を振り返っていきます。
- 「自我障害」とは?
- 「自我障害」を理解するポイント
- 「自我障害」が出た時の対策
以上3つの内容でお届けしました。

自我障害を理解するポイントや対策などをまとめましたので、何かのヒントになるでしょう。
この記事が、統合失調症の症状の1つである「自我障害」について調べている方の参考になれば幸いです。
自我障害についてはコチラの記事でも詳しく解説しています↓
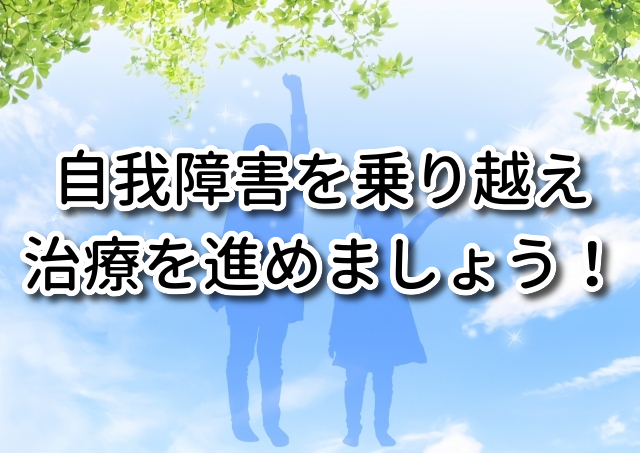
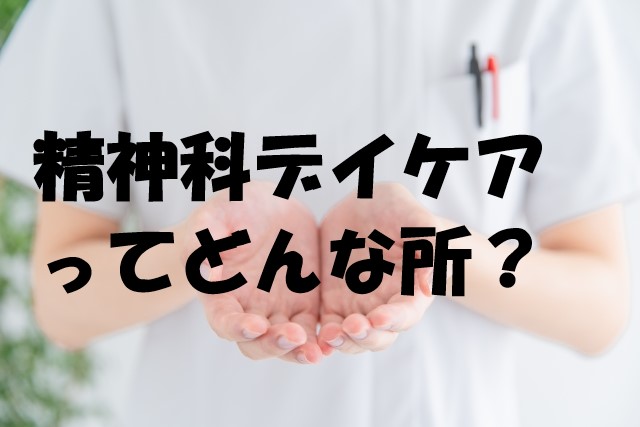






コメント